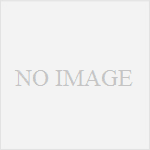写真 佐賀県鹿島市「救世神社」秋祭り 出典:鹿島市公式観光サイト
「かけうち」と呼ばれる鬼の面、黒い顔に尖った歯、口からは赤く長い舌。一度見たら忘れませんね。
 。
。
○日本武尊による熊襲退治
○日本武尊による東國の平定
○ヤマトタケルの妃と王子・王女
3.日本武尊による熊襲退治
熊襲国の首長取石鹿文(とろしかや)またの名川上梟帥(かわかみたける)を調略で持って滅
ぼし、滅ぼされた川上梟帥が「日本武皇子」の称号を奉る。
同記事について故古田武彦氏は『盗まれた神話p68~p72角川文庫』で“授号の公式”から著しく
違背していると指摘しています。
私の見解も同様で噴飯めいた記事と認識しています。なお同記事には「熊襲国」の位置を特定
する地名の記述もありません。
その後、日本武皇子は海路で倭に還り、吉備の穴濟の神・柏濟の神を誅殺した。孝霊天皇の皇
子吉備津彦こと桃太郎が吉備国を平定する過程で、鬼退治をした伝説が残されています。この鬼
とは、「吉備冠者・温羅」とされています。したがって、『紀』記事は吉備津彦に代えてヤマト
タケルを主人公に仕立て上げたのでしょう。
天足彦の王子ヤマトタケルについては、開化天皇の項で詳述しました。
4.日本武尊による東國の平定
景行天皇は吉備武彦と大伴武日連(おおともたけひむらじ)を日本武皇子の副将に任命しま
す。
出発に先立ち、伊勢神宮で参拝し、倭姫命から草薙劒を渡されます。
「神々の系図-平成12年考」によれば、倭姫命は贈崇神天皇ことツヌガアラシトの弟、倭彦こと
椎根津彦の娘黒砂(いさご)こと倭姫としています。
故百嶋氏の手書きメモによれば、「倭姫は川島大神の神霊に護られて“瀧原宮”をお守りしてお
られます」とあります。
川島大神とは、誰を指すのでしょうか。
「神々の系図-平成12年考」によれば、父系の祖は阿蘇系の天忍穂耳命、母系の祖は櫛稲田姫
です。
川島大神を祀る神社
瀧原宮所管社川島社 三重県多気郡大紀町
川島神社 名古屋市守山区川村町
祭神:イザナミ・大苫辺命・誉田別天皇・スサノオ・日本健命・大山津見神としています
が、本来の主祭神は女神の大苫辺命ともいわれています。
大苫辺命は『紀』が記す大戸之道尊(=スサノオ)と一対の神で、スサノオの妃櫛稲田姫と
考えられます。したがって、川島大神は母系の祖櫛稲田姫が最も相応しいといえます。
倭姫命を祀る神社は、
味島(あじしま)神社 佐賀県嬉野市塩田町 主祭神:倭姫命
写真 「味島神社」秋祭り 出典:鹿島市公式観光サイト
「彼岸花」が映えますね。

救世(くせ)神社 佐賀県鹿島市大字三河内甲 主祭神:倭姫命
皇大神宮別宮倭姫宮 主祭神:倭姫命
伊雑(いざわ)宮 志摩市磯部町 主祭神:倭姫命
ブログ“ひぼろぎ逍遥”を主催する古川清久氏によれば、佐賀県内で四社が倭姫命を主祭神とし
て祀られているとのアドバイスをいただきました。伊勢神宮の“斎王”となった倭姫命は佐賀県内
でも神として崇められていたようです。
ヤマトタケルの父天足彦は系譜上、スサノオの嫡子ナガスネ彦の妹瀛津世襲足姫を母としてい
ます。
瀛津世襲足姫は、ナガスネヒコの叛による恥を雪ぐため、九州王朝の忠臣として懸命に奉仕し
ました。
ヤマトタケルも父天足彦の弟建南方命が天皇家に叛を起こしたことを恥じ、父天足彦同様に九
州王朝の忠臣として懸命に働いたのです。
ヤマトタケルは伊勢神宮を出てから駿河焼津で“火攻め”に合うものの、草薙劒で難を逃れま
す。その後、相模国から海路で上総国に入る途中、時化に遭い、妃の穂積氏忍山宿禰の娘弟橘姫
(おとたちばなひめ)が海中に身を投げたことにより、危機を脱出します。
弟橘姫は「神々の系図-平成12年考」によれば、父物部宗家ウマシマチこと和知津見命、母は
息長(しな)姫(師長姫とも表記)としています。
ヤマトタケルは上総から陸奥國に入り、蝦夷の境に至り、嶋津神・国津神を平和裏に服従さ
せ、蝦夷を随伴し、日高見國から還り、常陸・甲斐を経て同地の酒折宮で休息をしたと記してい
ます。
同記事が記す「日高見国」は関東平野から一変して陸奥国に変更されています。
「日高見国」については、『日高見の源流-その姿を追求する著者菊池栄吾 イーピックス出
版社』をお読みください。
信濃國・越國は未だ皇化に従わないので、自ら信濃國を監察し、山の神を誅殺します。
吉備武彦は越國を監察しました。同記事には地名の特定性がなく創作記事と考えられます。
信濃を出て尾張に還り、尾張氏の娘宮簀媛(みやずひめ)を娶ります。
尾張氏は祖を天火明命(またの名彦火々出見命・饒速日命など)とあり、物部宗家系と推測さ
れます。
ある日、近江の五十葺山(いぶきやま)の荒ぶる神を知り、邪気を祓う劒も佩かず、単身で膽
吹山を昇ったところ、山の神大蛇と遭遇し、邪気が身を襲った事に気づきます。
その後、病は進み能褒野(のぼの)で病没し、伊勢國能褒野陵に葬られます。享年30歳でし
た。
ヤマトタケルは死後、白鳥となり倭國を目指して飛び立ち、降り立った地の二ヶ所、倭の琴彈
原(ことはずはら)・河内の舊市邑(ふるいち)に陵が造られました。
しかし、同記事には以下の不審があります。
(1)名古屋の熱田神宮から遠く離れた滋賀県伊吹山の荒ぶる神を単身で、それも武器さえ持た
ず退治に行くとは考えられません。おそらく、ヤマトタケルは既に病を得ており、将軍職を解
かれると共にヤマトタケル軍は解散されたと推測します。
ヤマトタケル軍を構成する百名を超す蝦夷等は、たちどころに職と住まいを失ったと考えら
れます。
(2)伊勢國能能褒野に葬られたとありますが、ヤマトタケルが天皇の皇子であれば“葬”の表記は
平仄が合いません。『紀』編纂者は、なぜこのような表記をしたのでしょう。
おそらく、ヤマトタケルが天皇の皇子ではないことを知っていたのでしょう。能褒野から遠
く離れた琵琶湖西岸の大津市神領にある建部大社(たけべたいしゃ)は本殿に日本武尊を祀
り、権殿には大己貴命とヤマトタケルの妃兩道入姫(ふたじにゅうひめ)と長子稲依別王(い
なよりわけおう)が祀られています。
この事実は、ヤマトタケルが琵琶湖西岸で亡くなり、妃と長子がヤマトタケルの祭祀を行っ
ていたのでしょう。
ヤマトタケルの死後、随行していた日高見国の蝦夷は倭姫命の元に預けられたものの、適応
性に欠け、奈良県桜井市の三輪山へ移動します。
しかし、神の山の木を切るなど地域社会に対応することができませんでした。
そのため、天皇の命によって、播磨・讃岐・伊豫・安芸・阿波の五カ国に移住することとな
り、その後、彼らは五カ国の佐伯部の祖となったとしています。
同記事の実態は、蝦夷等の移住地三輪山には彼らが期待した宿舎も仕事もなく、神の山の木
を伐採して宿舎を建設する行動に出たのでしょう。
大神神社を祭祀する物部氏は彼らの行動に不審を覚え、五カ国に分散して移住させたと考え
られます。
写真 滝原宮 皇大神宮(内宮)の別宮 三重県度会郡大紀町
出典:伊勢志摩観光ナビ

次回は「景行天皇」(4)です。