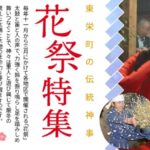写真 〔第55回〕鳥海山の残雪風景は日本一 出典:鳥海山・飛島 ジオパーク
○倭国から日本国へ禅譲
○天武天皇廣瀬大社・龍田大社二十五回の参拝
○吉野の盟約
○天武天皇への弔辞からみえるものは
1.倭国から日本国への禅譲
前話で天武十五年(686)に「倭国から日本国への禅譲」に触れました。
「禅譲に至る過程」について、日本書紀は「ヤマト一元史観」ですから記述するはずがありま
せんので、その点について検討してみましょう。
(1)禅譲とは
「権力の座を話し合いによって、その地位を血縁者ではない有徳の人物に譲ること」
具体的には、倭国王が日本国王に権力の座を譲り渡した事になります。
(2)倭国は何故「禅譲」したのでしょう。
最大の原因は「政治体制が弱体化し、維持することが出来なかった」ことに尽きます。
ヒントとなるのが『日本書紀-継体二十一年八月条』記事です。
「長門より東を朕(われ)が制し、筑紫より西を汝が制せよ。」
朕は継体天皇、汝は物部麁鹿火大連、領土を奪い取られたのが磐井で、歴史上「磐井の
乱」と呼ばれています。
おそらく、九州王朝の版図であった「長門より西」が、日本国の天武天皇によって制圧
されたと推測します。
制圧された最大原因は「筑紫大地震災害」です。倭国の首都「味経宮(小郡市上岩田遺跡
群)」は地震により倒壊し、首都機能を失いました。
・天武七年十二月是月条
「筑紫國、大地震が起こる。地割れは廣さ二丈、長さ三千餘丈、百姓の家屋、村ごとに多く倒
壊。」
また、九州王朝の版図であった「東国」も、この分断によって、情報が遮断され,九州王朝
との連携は不可能になったと推測します。
以上の理由から、九州王朝は禅譲せざるをえなかったと推測します。
(3)どこで「禅譲の交渉」が行われたのでしょうか。
おそらく「筑紫の太宰府」が交渉場所と推測されます。
「禅譲の交渉」は、天武十三年から開始されたと推測します。
(4)「禅譲の条件」
・「元号建元の権を移譲」」
天武十五年を「朱鳥元年」として建元。
是により、天武天皇は「詔」を発令し、「律と令」の公布を通じて行政権を獲得します。
・「外交権の移譲」
・「大宰府の接収」
九州王朝の都「大宰府」を明け渡します。
『二中歴―朱鳥元年記事』
「仟陌町収地又方始」
現時点で大宰府の面積は254000㎡と推定され、天武天皇は「方形」に均し たようで
す。
(5)最後の倭国王に対する処遇
北アジア・朝鮮半島では「地方の国王」に封じるのが通例のようです。
したがって、最後の倭国王も「○○王」として封じられたと考えます。
おそらく、九州や東国以外の西国に封じられたと推測します。
2.天武天皇廣瀬大社・龍田大社二十五回の参拝
同参拝の最初の記事
・天武四年四月十日
「風神を竜田立野に祀らせ、大忌神を広瀬の河曲に祀らせる」
何故、天武天皇は両社を頻繁に参拝したのでしょうか。
両社への参拝は毎年4月・7月の例祭に合わせて行われていたようです。
(1)廣瀬大社 奈良県北葛城郡河合町大字川合
別名 廣瀬坐和加宇加乃賣(ひろせにますわかうかのめ)神社
主祭神:若宇加能売命(わかうかめのみこと)
相殿神:櫛玉命
ご神徳:大忌神(瀬織津姫か?)
通説は若宇加能売命を豊受姫としています。豊受姫は伊勢神宮外宮の主祭神豊受大神と同
一神で、別名に「女鍛冶神」があります。
社伝に依れば相殿神で祀る櫛玉命は物部氏の祖とされる饒速日命としています。
両神は夫婦神でもあります。
『記紀神話』によれば、大忌神は「伊弉諾が黄泉の国から帰還した際、穢れを払え浄める
神、“神直日神・大直日神”の二神」としています。
故百嶋氏の「神社考古学」では、以下の二神としています。
・神直日神
鴨玉依姫 父は豊玉彦(大幡主の嫡男) 母は櫛稲田姫(金山彦の嫡女)
・大直日神
大山咋(おおやまくい)神 別名:熊甲安羅鍛冶彦・都怒賀安羅斯登・「真の大物主」
父は天忍穂耳命 別名:天児屋根命・志那津彦・贈孝昭天皇など
母は市杵島姫 別名:須勢理姫・瀛津島姫など
東北地方各地には大物忌神を祀る神社があり、代表的な神社が鳥海山大物忌神社 山形県
飽海郡遊佐町
ご祭神:大物忌神
社伝などによれば、通説の豊受姫と違い、「大物忌神を大物主」としています。
写真 〔第55回〕鳥海山の残雪風景は日本一 出典:鳥海山・飛島 ジオパーク

私見は廣瀬大社の鳥居「三つ鳥居」に注目しています。
三ツ鳥居は別名「瀛(いん)鳥居」と呼ばれています。
したがって、廣瀬大社は「瀛氏金山彦」との関わりが見えてきます。
その候補神は、「鴨玉依姫とその夫神大山咋」となります。
詳しくは、第二十五話「4.大神神社との関わり」をお読みください。
写真 廣瀬大社 鳥居の下部を注視してください。

(2)龍田大社 奈良県生駒郡三郷町立野南
主祭神:(右殿)天御柱命 (左殿)国御柱命
ご神徳:風の神
社伝によれば天御柱命は「級長津彦命」、国御柱命は「級長津媛命」とされています。
故百嶋氏の「神社考古学」では、以下の二神です。
志那津彦命 別名天忍穂耳命・天児屋根命・大年神・草部吉見神・贈孝昭天皇・海幸
彦・犬飼神など
志那津姫命 別名天細女命・豊受姫・女鍛冶神など スサノオの娘。
「風の神」に最も相応しい神は「志那津姫命」と考えられます。
理由は「鍛冶には強い風が必須の条件」と考えられるからです。
伊勢神宮(正式には皇大神宮)内宮境内摂社に「風の神」を祀る
風日祈宮(かざひのみのみや 元の名は風神社、「元寇」襲来の際にご神徳である
「風の神」が蒙古軍を撃退したことを賞して社名を変更)
主祭神:級長津彦命・級長戸辺命(=豊受姫)
両神は、一時夫婦神でしたが別れ、饒速日命別名彦火々出見命・山幸彦と一生を添
い遂げました。
以上から、「風の神」は通説通り、「志那津彦命・志那津姫命」で間違いないようです。
(3)天武天皇が廣瀬大社・龍田大社を拝んだ理由
両社の主祭神を検証した結果、天武天皇の遠祖は「神直日神こと鴨玉依姫と大直日神こと
大山咋」と推測されます。
この両神は「九州王朝倭国第三代国王孝霊天皇」を支えた最大氏族「白族(後の紀氏)と瀛
氏」の血筋を濃厚に受け継いだ神といえましょう。
3.「吉野の盟約」
・天武八年五月二十五日条
「天武天皇・鸕野讃良皇后、六人の皇子」草壁・大津・高市・忍壁・川島・志貴皇子)と共
に吉野へ行幸。皇后の誓いは(草壁皇子を後継者とすること)天皇の如し。」
天武朝の成立は、第一王子の高市皇子の活躍が大であることを日本書紀は詳述しているに
も拘わらず、鸕野讃良皇后の御子草壁皇子を後継者とする論理性を持ち出し、他の五人の皇
子に誓わせたという内容です。
・天武十年二月二十五日条
「是の日に、草壁皇子尊を立てて皇太子とす。」
「吉野の盟約」を実現した記事です。
・朱鳥元年九月九日条
「天皇の病、遂に癒えず、正宮で崩御」
ところが、『二中歴・麗気記私抄・海東諸国記・六郷山(屋山)年代記』は朱鳥年号九年間」
としています。
不思議ですね。
「朱鳥元年」は、天武天皇薨去後に、新たに元号を「朱鳥」に改められたとする
蓋然性が高いと思いませんか。
4.天武天皇への弔辞からみえるものは
(1)“壬生(みぶ)のこと”大海宿禰麁蒲(おおあまのすくねあらかば)
“壬生”について、日本書紀補注は「天武天皇の幼少時代を養育した乳母の子、すなわち
大海宿禰麁蒲を乳母兄弟」としています。
”壬生“の意味には、同じ出自とする一族や集団を指すとあります。
大海麁蒲の別記に「凡海麁鎌(おおあまのあらかま)」があり、「凡海氏」は安曇氏の一
族と云われています。
『新撰姓氏録』は「右京神別下 摂津国神別」とあり、摂津国を本拠地としていたとあり
ます。
日本書紀補注に従うと、天武天皇は摂津国で養育され、安曇族と同じ一族と云うことにな
ります
「百嶋神社考古学」では、安曇族の祖は安曇磯良で、父はウガヤフキアエズ別名味鋤高彦
根命、母は鴨玉依姫とあります。
安曇礒良は父の“大矢口物部軍統領の座”を継がず、開化天皇の忠実な家臣として働き、別
名「第一次住吉神こと表筒男命」と呼ばれました。
安曇礒良は西日本各地の海人(あま)集団を率い、後には新潟県の姫川を遡り、信濃國へ
入り「安曇部」を設置します。
近年の研究では、「六世紀以降、蘇我氏が東国に屯倉の設置を進める中で蘇我氏と深い主従
関係を築き、安曇部は屯倉管理に特化します。屯倉が置かれた場所には、イヌカイ地名とミヤケ
地名が近接していました。
したがって、大海宿禰荒蒲は安曇氏の末裔かつ海人集団の長で、瀬戸内海~難波の海まで勢
力を伸ばし、本拠地を摂津国としていたようです。
安曇氏の統領阿曇比良夫(日本書紀では阿倍比良夫と表記)は、662年白村江の戦いで戦死した
ことを受け、安曇氏は一層、九州王朝倭国と距離を置きます。
既に摂津国へ進出していた一族は、蘇我氏との関係を一層強めたようです。
おそらく、天武天皇は青年期まで安曇氏と共に北部九州で生活していたと推測されます。
また、天武天皇も安曇氏と同様に九州王朝に見切りを付け、名目を就けて近江朝に近づ
いたと推測します。
天武天皇の素性は海人集団の長、安曇氏と主従関係にあり、蘇我氏とも密接な関係のある人
物で、九州王朝倭国王家の血筋をひく人物かもしれません。
その候補者として、栗隈王の長男“三野王”ではないかと推測します。
この推測は一例に過ぎず、今後の研究成果を待ち望んでいます。
(2)“諸王”のこと 浄大肆伊勢王
・天武十四年(685)正月二日条
「明位二階、浄位四階、階毎に大廣有り。併せて十二階。諸王の上位の位。正位四階・直
位四階・勤位四階・追位四階・進位四階。階毎に大廣有り。併せて四十八階。諸臣の位な
り。」
日本書紀は「諸王の冠位」基準についての記述がありません。
伊勢王の冠位「浄大肆は諸王十二階の序列第十一位」に相当しますが、上位の明位二階は
天武天皇の兄弟や皇子、浄位一~三階までは皇孫・皇曾孫で占められていたと推測され、親
王の範囲には入りませんが、親王以外では、最高位に相当する冠位と推測します。
日本書紀が記す伊勢王に関する記事
①斉明七年六月条(661年)
「伊勢王薨去」
②天智七年六月条(668)
「伊勢王とその弟王続けて薨去。官位を未だに公表されていない。」
③天武十四年十月十七日条(685)
「伊勢王等、亦東国(経営)に向かう。」
④朱鳥元年九月四日条(686)
「親王より以下、諸臣に至るまで、ことごとく川原寺に集い、天皇の病平癒
を誓願する。」
⑤持統二年八月十一日条
「(天武天皇の)葬儀を浄大肆伊勢王に命じて宣正させる。」
①と②の記事は重複記事と考えられます。
③以降の伊勢王は二代目の伊勢王かもしれません。
伊勢王は諸王を代表しての弔辞、葬儀執行責任者を託される程の人物ですが、官位について未詳
のままです。
もしかすると日本国誕生に先立つ九州王朝倭国王の後継資格を持っていた人物かもしれません。
(3)“宮内”のこと 直大三肆犬養宿禰大伴
「直大三肆は冠位四十八階では序列第十三位」に相当し、現代で云えば秘書官と考えられます。
天武天皇にとって信頼の篤い人物であったようです。
(4)“左右大舎人”のこと” 浄大肆河内王
天武天皇が抜擢した直臣大舎人を管轄したのが直大三肆犬養宿禰大伴と考えられ、伊勢王よ
りも冠位は上位です。
以上の検証から、朧気ながら天武天皇の血筋がみえてきます。
ア.天武天皇の両親
父舒明天皇 母寶皇女(後の皇極天皇 重祚した斉明天皇)の皇子ではありません。
イ.父は九州王朝の重臣栗隈王と推測します。
ウ.若き頃に、「三野王(美濃王とも表記)」を拝命します。
エ.「白村江の戦い」に敗れ、唐軍に占領された九州王朝を見限り、九州の地を離れ、新天地へ
向かう決意をします。
オ.協力者は蘇我氏・安曇氏・事代主系物部軍と推測します。
次回は「高市天皇説」です。